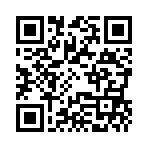2009年08月31日
クーヨン9月号
もうそろそろ10月号が発売されちゃいますが、9月号を買いました。
特集は「子育てに生かすモンテッソーリ教育」↓

モンテッソーリは「教具」を用意してお仕事をやらせる、というところが何となく腑に落ちていないのですが、
「平和のための教育」「敏感期」などのキーワードは気になるのでもっと詳しく知りたいなと思って、
数か月ぶりに購入。
読んでみたら、今までよりも「いいじゃん」「なるほど」と思う部分は増えました。
たとえば、
・早期教育でなく適時教育
・数を教えるにしても、ただ数字として表わす部分だけじゃなく、子供の中の秩序感の生成から見守る
・教具は整然と置いておけば子どもはその通りに片付けるようになる
とか。
でも、6か月過ぎから鏡を置いて自分を認識させる、なんていうのは、
シュタイナーの「7歳までは夢の中」説が素敵
 と思う私にとっては
と思う私にとってはそんなわざわざ目覚めさせなくっても!という感じがします。
「教具」の数々にしても、なあんか自然じゃないというか、
「子どもに手を貸すだけ」にしてはちょっと大人の意図が見え透いている感じがするんだよなあ。
ともあれ。
マリア・モンテッソーリさんはイタリア・20世紀初頭生まれ。
「こどもの家」を始めた当初はムッソリーニから庇護を受けていたんだけど
独裁者になったのを見てそれを拒否。すごい!
迫害を逃れてスペイン・オランダと渡り歩いた後
インドに招かれ7年間で1000人を超える教師を養成。
「子どもの家」を各地につくりました。
その験から、平和が大事!という境地に至って
「世界には戦争ではなく、平和をつくるための教育が必要」
「平和は子どもからはじまる」
「子どもが居場所を得て環境を愛することが平和に繋がる」
という結論に至ったんだそうです。
どの言葉も今を生きる私たちにこそ必要に思えてなりません。
優しくてパワフルなおばあさまだったんだろうな、と想像します。
きっと、傍にいたらシュタイナーより好きに違いない。笑
モンテッソーリの平和教育には共感するし
細かい点では「なるほど
 そのアイディア使える♪」と思うことが多々あるけど
そのアイディア使える♪」と思うことが多々あるけどやっぱり全体としては私の中ではシュタイナーに軍配が上るな

というのが感想でした。
2009年08月30日
手仕事
手芸が大好き(あまり上手ではありませんが)な私にとって、
赤ちゃんがいると危なくて針仕事ができないのは結構ストレスでした

ミシンなんか特に起きてると危ないし寝てると音で起きるし

今朝は夫が遅起きで、娘と静かに過ごしているうちに
ふと、何となくできそうな気がして道具を出してきてみたのです。
そしたら、じゃれつくでもなく自分で絵本をめくったり
座椅子に座っている私の肩にもたれて手元をじっと眺めたりと
全然やめさせられることなく夫が起きてくるまでの1時間半ほど刺繍が進んだのでした☆
今作っているのは、フランス刺繍付きの巾着ポーチ。
9月末の義母の誕生日にとスパートかけていますが
実は春からやってます。笑
なかなか進まず間に合うのかしら?!と焦っていましたが、
娘がこの調子なら何とかなりそう!
私は子どもと一緒に遊ぶのが苦手で、
性格上どうしてもすぐに片付けようとしてしまったり
積み木を秩序立てて並べてばかりしてしまったりするので
むしろ邪魔せず一人の世界に没頭させてあげていることがほとんどなのですが、
娘に申し訳ないような気持ちになることもありました。
それが、シュタイナー的な幼児教育の本では一緒になって遊ぶ必要はなくて、
見守りつつ大人は大人の手仕事を傍らでやっているのがよしとされているのを読んで
なんだあ~よかったんだあ、とホッとしたものです。
今朝の時間は、そんな私にとって感激モノでした

まだまだ無理かと思っていたけれど、子どもはちゃんとわかってくれるのだという実感が増した出来事でした

2009年08月29日
森のようちえん体験会
熊本に森のようちえんがあったなんて~☆
うるるんか何かで見て体験してみたい
 とずっと思っていました。
とずっと思っていました。今回私は参加できませんが(やりたいことが多すぎてバッティングだらけ・・・)
定員まであと少しらしいので興味のある方はお早めにお問い合わせください!!
ここから↓
**********************************
立神峡公園にみんな おいでよ!!
森のようちえん無料体験会
~大切にしよう!ひとりひとりのセンスオブワンダー~
秋のいりぐちを感じ取れる季節。里山をゆっくりお散歩しながら、自然と触れあいたい…♪
ゆったりお散歩をして深呼吸。里山の自然を感じ、心も身体もいっぱい動かしながら、
五感をいきいきとつかって楽しみませんか?
<日程>
2009年9月12日(土)or19日(土)
ご都合のいい方にお申し込み下さい。
<時間>
両日とも10:00~11:30 (受付9:30~)
<場所>
立神峡公園熊本県八代郡氷川町立神648-4
集合は立神峡里地公園管理棟横の研修室です。
(場所がわからない方はお問い合わせください。)
<お問い合わせ・お申し込み>
電話&FAX : 0965-62-1543 (担当こうやま)
メール : tategamikyou@yahoo.co.jp
ホームページ : http//www.tategamikyou@yahoo.co.jp
<対象>
おおむね6歳未満のお子さまと子育て中の 保護者の方、および保育関係者、自然活動、 運営ボランティアなどの参加も歓迎です。
<体験会でのプログラム>
10:00 集合 (9:30~受付)
10:10 これまでの 森のようちえんをスライドでご紹介!
10:30 晴れていたら河原でお散歩、雨だったらカッパを着て長靴はいてお散歩
11:00 おたのしみのおやつ
<持ち物>
晴れの場合 : お着替え・タオル・帽子・川遊び用のぬれてもいい靴もしくは 『かかとがある』『とめがある』 などのぬげにくいサンダル。
雨の場合 : カッパ ・長靴・ お着替え・タオル
この取り組みの目的は、幼児本来の豊かな感受性を育み、自然や自分他者に対して思いをめぐらす心をはぐくむ事。そして取り組む姿勢として保護者も保育者も地域の大人すべてが、自然からの学び、気づきを大切にする事、子どもの持つセンスオブワンダーをはぐくむ意識を持続していく事等を考えています。
“センスオブワンダー” 子どもは、神秘的なものや不思議なものを感じ取る力をもともと持っています。
大切な事はそばにいる大人が子どもといっしょになってわかちあうことができること…
レイチェル・カーソン著「センスオブワンダー」より要約
おまちしてます
******************************
↑ここまで
2009年08月27日
にじみ絵教室作品展


・日時 : 2009年9月14日(月) ~ 10月2日(金) の間の平日の 11:00 ~ 17:00
*土日祝日休みです!
・場所 : ギャラリーカフェクミン(八代市永碇町961-1 障害者福祉施設まんさく園併設)
↑クリックするとHPにジャンプします
・内容 : にじみ絵作品
教室の制作風景スナップ写真
にじみ絵が乾く前の写真(乾く前がベストの美しさだそうです。たしかに!)
にじみ絵とシュタイナー教育の説明
にじみ絵を使った子どもたちの工作
クミンさんは先日の教室の帰りにたまたま通りかかりました。
静かな住宅地の中のジャパニーズモダンな雰囲気のお洒落な建物でしたよ☆
カレーとかも美味しそうですね~

昨日も書いたように、お見せできる感じに仕上がらなかったので私は出品しません
 が
が素敵な作品がいっぱいだと思います

ぜひ見に行ってみてください。
2009年08月26日
にじみ絵教室に行ってきました
熊本市からはちょっと距離がありましたが、
今回はねむかおりちゃんが車に乗せていってくれたので
楽しくおしゃべりしながらあっという間の道中でした♪
ベビーシートを貸してくださったかおり@おうちギャラリーさん、ありがとうございました☆
今回の講座は、講師の鈴木裕子さんが大津在住ということで八代からは遠い!
じゃあ八代に招いて企画しよう!という八代の皆さんのバイタリティの結晶

お子さんがいらっしゃりながら、
絵の具に画板、水入れ用の空きビンなどを何十人分も用意して・・・
とっても大変だったと思うのに、とっても楽しそう♪
子どもたちの面倒も見てくださって、本当に助かりました!ありがとうございます

別れ際に
「何かやる時はこれ一式貸しますよ~」
なんて言われて、えっ?!いいんですか!じゃあ熊本市でも何かしなくちゃ!!
という気にならされちゃいました

さて、講座ではまず黄色の絵の具が配られ、
濡らした画用紙に色の声を聞いてどこに描かれたいと黄色が思っているのか感じながら
すーっとやさしく筆を降ろしていきます。
濃いところ、淡いところ。
絵の具を乗せるところ、絵の具を溶いた色水でぼんやりさせるところ。
私はぽたっと垂らしてみたりしました。
次は山吹色。(私、子供のころずっと「やまぶ黄色」だと思ってました
 だって黄色なんだもん
だって黄色なんだもん )
)同じ黄色でもさっきまでより絵があたたかくなります。
この辺で娘が興味津々で膝に乗ってきて、筆を触りたい!絵の具つけたい!と主張し
筆の角で画用紙を引っ掻いてたくさんキズがついてしまいました

最後に青。
塗る前に絵の具自体をじーっと見て色を観察して、青さんが行きたそうな場所を探ります。
だんだん黄色と混じって緑色になりすぎ、余白を残しておけばよかった、とちょっと後悔。
ここに載せようと思っていましたが、お見せできる感じには出来ませんでした

まあでも、娘との初合作ということだけで感動です☆
完成したら、みんなでそれぞれの絵を見て回り、感想を述べ合います。
本当に同じ道具で同じ色しか使っていないでこんなにも一人一人の出来上がりが違うものかと
前回「虹の雲」さんで初めてにじみ絵を体験した時にも同じことを感じましたが、
今回は色自体を体験する」ということが目的で(虹の雲では「魚」がテーマでした)
抽象画のような自由度の高い絵だったので、余計にそれが強く感じられました。
最後に、講師の裕子さんから配られたプリントの内容をご紹介します。
↓
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シュタイナーの色彩に関する言葉
黄・青・赤は輝く性格を持ち、その中で何かが光り輝く
黄は霊の輝きである
青は魂の輝きである
赤は生命の輝きである
*{黄は放射しようとする} {青は内に向って輝く} {赤は私に静止した赤色として作用する}
そういう色の本質を把握し、色そのものの中に、いわば色の意思を認めようとすることが大切です。
物体の表面にまで降りてくるものが色彩であるとすれば、人間を物質的なものから引き上げて、
霊的なものまで導いてくれるのも、色彩なのです。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
裕子さんは「まあ、理屈は置いといて」という感じで難しい話はされませんでしたが、
色を体験した後にさりげなく配っていただいたこれを読むと、ああ、たしかにそうだわ、と実感が湧きます。
参加された方それぞれの活動の告知で、素敵なイベントがいろいろあったので、
ぜひ近々こちらでもご紹介させていただきます♪
乞うご期待☆
2009年08月15日
「おおきなかぶ」

我が弟が、姪っ子(私の娘)のためにお盆の帰省のお土産として買ってきてくれました。
前回帰って来た時に、何かの話から
「よし、今度『おおきなかぶ』を買ってきてあげよう
 」
」と宣言してくれていたので、この挿絵のイメージが湧いて早速ネットで検索

有名な話だから他にもあるのかもしれないけど、ぜひとも福音館のこのバージョンがいいなあ、
と思っていたら、まさにその通りのものだったので感激!
弟、ナイスチョイス

幼稚園の年中の時、学芸会で孫娘役をやったのでなんだかとっても親しみのある「おおきなかぶ」。
デッサンの精確さを感じさせつつ情緒ある挿絵が素敵☆
疲れて腰掛けてるおじいちゃんとおばあちゃんが何とも言えません

中身の絵とはギャップのあるタイトルの扉絵もナカナカのセンスです

裏を見たら800円でびっくり。
と思ったら、「ぐりとぐら」も800円でした。
絵本って、フルカラーなのに安いのね!(ものによる?)
著者を見ると「トルストイ再話」って。
再話ってどゆ意味?元々ロシア民話なのをトルストイが掘り起こしたのかしら。
トルストイも小学生の頃かなり図書館で借りて読んだので親しみあり。
内容は全く一つの話も覚えてないけど・・・
母に「トルストイ読んだら?」的に促されて借りていた気がするなあ。
娘はというと、弟のところに絵本を持って行って膝に乗せて!と要求し
これを読んで!と指さして何度も読んでもらっていました。
「うんとこしょ どっこいしょ」
の繰り返しが小さい子にも楽しいのでしょうね♪
2009年08月14日
「シュタイナー入門」

新書。
やわらか~くかみくだいたシュタイナー教育についての本しか読んだことがなかったので
広く深い人智学ってのは一体どんなもの?それからシュタイナーさんってどんな人?
というところを広く浅く知りたくて、買ってみました。
が、それは無理なことでした。
むずかしー!!んです!
私の読書の時間は夜布団に横になってからなので、
何度も「??どこまで読んだっけ?」と辿らないと意味がわからない。
ゲーテとかフィヒテのあたりは、だいぶ根気強く何度も読み返してみたけど
やっぱり意味不明・・・悔しい!
世界史大好きだったのになー。山川の教科書引っ張り出したくなりました。
あと数ページで終わるので、とりあえず読み終わってから。
勢いがないと読み終えられそうにない

入門でこれじゃあ、シュタイナーの著書なんて読めるのか?!
難しい難しいと言われるので、いつかは!と思っているけど、道のりは遠い

でも、この著者はなかなか魅力的でした。
この人が大学のゼミの教授だったら、変人だけど授業は面白そう。
さて、難しすぎてまとめきれないので、紹介文を引用↓
「シュタイナー教育」や「人智学」で日本でも広くその名が知られるルドルフ・シュタイナー。
だが、アカデミズムからは「胡散臭いオカルト」との烙印を押される一方、
受容する側にも、その思想への盲目的な追従、偶像化が見られるなど、
ここ日本でのシュタイナー理解はまだ充分とはいえない。
彼が立脚した第一次大戦下ドイツの時代状況、
また、ドイツ精神史における思想系譜、歴史経維に広範な省察を加え、
その生を内側から活写することで、
「みずから考え、みずから生きること」への意志を貫いた「理念の闘士」、
シュタイナーの思想的核心を浮き彫りにする。
第1章 教育思想の源泉―他者への目覚め
第2章 認識の探究者―カント、フィヒテ、ゲーテをめぐって
第3章 それは「オカルト」なのか?―西洋と東洋の霊性史
第4章 神智学運動へ―ブラヴァツキーの闘い
第5章 ドイツ精神文化の霊学―純粋思考と帰依の感情
第6章 戦争と廃墟の中で―「国民」になる以外、生きる道はないのか!
第7章 魂の共同体―ナチスの攻撃と人間の悲しみ
ここまで↑
よくわかったことは、幼児教育は彼の真ん中にあったことではないということ!
それから、かなり理屈っぽい人間であること。
彼の思想を理解するには、彼の時代までのキリスト教のあり方を知る必要がある。
ローマカトリック教会が正統を保つため異端や異教を弾圧してきた結果、
その多様性は隠れざるを得なくなり、オカルティズムとしてひっそり生きてきた。
そのように一部の人間(カトリックでは神父)だけに神(=霊的なもの)との
交信が限られてきた当時までのキリスト教ではなく、
すべての人に開かれたものにしよう、というのが彼のオカルティズム。
この場合の「オカルティズム」は、日本で一般的にイメージされる「オカルト」とは全く意味が違う。
「オカルト」の語源は「隠されたもの」。
ちなみに日本では宗教的多様性が維持されてきたので
ヨーロッパと同じ意味でのオカルティズムは存在しないと著者は言っています。
唯物論否定。
だからといって、スプーンが曲がるみたいな、物質的にわかりやすいことに
その表れを求めるのは精神的退廃である?
直観よりも考えて考えて考え抜いたところに霊的なものとのつながりがある?
これがシュタイナーを知ろうとすれば避けては通れない彼の思想の真正面なんだって。
私の理解が悪くてニュアンス多々間違ってるかもしれませんが
しかし、教育だけに一生懸命な人生だったわけじゃないのに
それぞれの分野で一目置かれる功績を遺していったなんてすごいなあ。
むしろ全般的に考えていた人だからこそ、すべての分野にそれが活かされているのかもしれない。
もっとバイオダイナミック農法のこととか医学のこととかも出てくるかと思ったけど
この本はシュタイナーの思想を語る本だったので、その辺は全然載ってなかったのが残念。
次はその辺にも触れている本を読みたいな
2009年08月12日
「ペレのあたらしいふく」
娘の保育園の貸し出しで自分が読むために借りてきました。

娘は、文章が長すぎて食いつかず。あと1・2年、いや3年後くらいかな?
お説教がましいところはひとつもなく、
ものが自分の手元にやってくるってどういうことなのか、
ちゃんと目に見えるように描いてくれています。
レトロチックなタッチも好み

背景の細かな描き込みが楽しい。
そして労働の尊さ、人とのふれあいの中にこそ存在する生活。
一時期はまって読んでいた「大草原の小さな家」シリーズや
大好きな「赤毛のアン」シリーズに通じるものを感じます。
是非とも欲しい1冊になりました!
後から、著者ベスコフは、私の大好きな松井るり子さんの大好きな絵本作家だったことを知って、納得!!
2009年08月11日
ヴォルドルフ人形手作り同盟

でも、
他にもたくさん人形は持っているし・・・
結構いいお値段するし・・・
作り方見たらかなり大変そうだし・・・
出来上がりを買っちゃおうか?
でも、せっかくなら作ってあげたいし・・・・
とかとか!
ひとりでぐるぐるしていたのですが、
先日キューピーちゃんを抱っこして、ぎゅーってしたり、歩きながらよしよしとあやしている娘を目撃してふっとびました。
か、かわいい


もうそんな時期?!
キューピーちゃんでも可愛いけど、これが自分のつくった自然素材のお人形だったら可愛さ100倍

こりゃ迷ってるバアイじゃない!!
やるぞー!オー

と、テンションあがった私。
しかし、やっぱり一人では遠い道のり・・・

そこで、最近シュタイナー的な子育てに興味を持ってよく話をしている
お友だちのねむかおりちゃんを誘って、一緒に挑戦することにしました☆
ひとりではなかなか手が出なかったけど、励ましあいながらぼちぼち作ってみよー

てことで、手作りキットをネットで検索したところ。
大きさやら何やら、いろいろ種類があるのね~。
ネットでも買えるけど、イマイチどれが合うのかとか難易度がわからないわあ

いくつも作る自信はないから、どうせ作るならずっと可愛がれる子にしたい。
来月、福岡に行く予定なので、シュタイナー関連商品を置いているお店で
年齢やその子によってどんなのがいいのかアドバイスしていただいてから決めようと思います☆
2009年08月10日
「よあけ」
貸出は2冊まで。
以前から読みたいと思っていた「よあけ」を見つけたので、自分用に一冊借りちゃいました☆
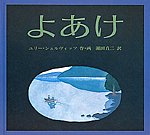
静謐な朝の空気をそのまま切り取ったような絵本。
添えられた言葉も絵も詩の一部のよう。
主人公はどちらでもなく、自分のイメージの中にある夜明け。
自分でも忘れているいつかの夜明けへの、旅の入口となってくれます。
ちょっと中国っぽさを感じていたら、やっぱり宋時代の中国詩をモチーフとしたものでした!
色の放出が眩しい最後のページは、
色づかいがシュタイナー教育で用いられるにじみ絵に似ているなあと思いました。
淡々としたページが続いているところに突然ぱあっと光が射して、一瞬ドキン!
心をぐっと掴まれました。
借りるだけでなく、欲しくなっちゃった(>_<)
2009年08月09日
決心
もう、娘の前ではPCを開かないぞ!
というのも、TVはほとんど点けない私ですが
その分情報はインターネットに頼っているところがあり・・・
家計のために新聞も取ってないし(^_^;(共働きのため、どちらも会社で読んでいます)
一方的に流される情報よりは、自分で選べる感があります。
しかししかし、ついにとうとう、娘がクリックできるようになってしまったのです。
絶対、中学生にちかくなるくらいまではいじれるようにさせない、と思っていたのに。
まだわからないだろうと思って、抱っこしながらブログを更新したりしていたのがいけないのです。
触りたい時に離そうとするとバタバタ・キーキー言って怒ります。
親がやっていることは真似したくなるに決まっているのだから、
娘に触らせたくないなら自分がいじっているところを見せなければよかったのです。
わかっていたのにやめられなかった私が悪い!
なので、手始めにパソコンに布を被せて普段は見えないようにしました。
そして、娘が眠ってからスイッチを入れる。
起きたら途中でも保存して切り上げる。
ルールをシンプルに考えたら、まだ数日ですが続けられるようになりました。
更に確固たるモノにするため、ここで宣言させてもらった次第です

2009年08月08日
「もこもこもこ」

もっと娘が小さいころ見せても無反応だったのに、
1才過ぎた今はこの絵本が一番のお気に入り。
何度か読んであげていたら、最近は部屋に落ちているのを見ると拾ってきて
自分で
「バフンッ!ボム!ダーッ!」
とか何とか効果音付きで音読しています。笑
こういうシンプルなものに反応がいいと、親の勝手乍ら嬉しくなっちゃいます。
私はこの本を初めて見た時は、微妙に不協和音的な色合わせに胸がざわついて
何だか好きになれない気がしていたのです。
それが、娘にせがまれ何度も何度も味わううち、美しいグラデーションのページよりも
そっちの違和感の方が気になってじーっと見入ってしまうようになりました。
色彩もさることながら、言葉と造形どれをとってもぴたりと当てはまる。
詩人の仕事だあ~。
さすが谷川俊太郎。
この本を見て、谷川俊太郎の守備範囲の広さに夫と驚きました。
鉄腕アトムの歌の作詞も彼なんですってー。
きっと物凄いバイタリティの持ち主なのだろうと想像します。
写真も、ピカソにそっくりの目をしているし。
谷川俊太郎をテーマにしばらく追いかけてみる気になっています。
2009年08月05日
夕陽がキラキラ
降りたバス停からの間に、保育園に隣接する寺の墓地を通ります。
毎日お墓なんて嫌だなあ、なんて思えないこの墓地。
毎日気持ちよい風が吹きぬけるたびに死者が眠っている墓が持つ生々しさを風化させるらしく
穏やかな老人のような顔を見せています。
ただ古いだけじゃなくて、人の手がほどよく入っていて大事にされていることも
この雰囲気の源なのでしょう。
7月の盆前には何人もの方が草取りに来られていて、日に日に地面が見えてくるのには驚きました。
その土にも、長雨とこの暑さで週末明けにはまたわさわさ草が

その日の空気と同時に、ダイナミックに移ろう四季も感じられます。
こんな墓地は初めてです。
「アンの愛情」(出たアンフリーク
 )や「虹の谷のアン」で
)や「虹の谷のアン」でやたらにモンゴメリ(著者)が「気持ちのよい墓地」を細かく描写していて
「そんな墓地あるの??」と訝しんでいたのを、
「これのことかあ」
と、一人で通路を歩きながらよく思い出します。
さて、その墓地の門に向って歩くと、今の時期は必ず夕陽が飛び込んでくることになります。
まるで、天国に続く道のようです

私は、夕焼けを見るのがそれはそれは好きだったのです。
それを、夕空を見て思い出しました。
思えば、夕陽に向かって帰り道に歩くなんて、何年ぶりでしょうか。
いや、学校より東側にしか住んだことがないばかりに、
夕陽を見るには振り返り振り返り歩くしかなかったことを今思い出しました。
その代わり、高校生の頃、自転車を漕ぐ背中いっぱいに夕陽を浴びながら、
「あ、私たち今、黄金色の光の中を走ってる!!」
と確信に満ちた気持ちを全身で感じた瞬間をはっきり覚えています。
これが青春なんだ!と

夕空を眺めるブームは中学生の頃がピークで、
通っていた学習塾の休み時間になるとすぐ外に出て空を眺めていました。
オレンジ色の空よりも、それが終わった後の青と金色の間のエメラルドグリーンの瞬間を捕まえたい一心で、休み時間がずれていると
「今日は見れなかった・・・
 」
」と悲しくなっていました。
夕空を眺めずにいる人たちを
「よくこんなに美しいものに目を向けず、よく仕事(勉強)なんかしていられるなあ!」
「毎日こんなに素晴らしいドラマが繰り広げられていることに、何故もっと世の中は注目しないのだろうか?!」
と真剣に考えていました。
と、夫にこの間言ったら
「本気で他の人は興味ないって思ってたわけ?」
と呆れ顔をされました。そうそう。笑
この独りよがりが青春の証って感じがして我ながら愛おしいです。
夫も、彼なりの夕空との時間を過ごしていたそうです。
そんな私も、大学生になり夕方起きて朝寝る
 破綻した生活を経て深夜帰宅のサラリーマンに突入し
破綻した生活を経て深夜帰宅のサラリーマンに突入し夕方空を見る余裕を失くしてから早12年が経ち、
やっと夕空に目を向けられる生活を手に入れることができたというわけです。
これも娘が生まれてくれたおかげ!!ありがとう娘よ

こうやって、子どもは生まれてくることで、直接子育てに関係しないことでも
親のところに思わぬプレゼントを持ってきてくれているような気がしてなりません

これから季節とともに、毎日少しずつ空の表情も変わることでしょう。
薄暗い墓地は想像するとちと怖いのですが、
それもまたをかし、なのかもしれない?と、楽しみです。
2009年08月03日
言葉の萌芽
(「おっぱい」を差す言葉という意味で、 実際は「おんまい」「うんまい」「おんま」「うんま」など)
だけでしたが、最近数が急激に増えてきました。
・「ばあー!」
いないいない、と言うと続けて「ばあー!」と言います。
自分からもいないいないばあー!をしてきます。
・「シーッ」
トイレでシーシー声掛けてたら、トイレに行くと自分で「シーッ」と言うように。
だからといって完全にオシッコ=「シー」とは結びついていない模様。
単に「ここは『シーッ』と言う場所だ」という認識のようです。
絵本「もこもこもこ」の「シーン」としたページで「シーッ」と読んでいたら
娘が自分でめくる時には「もこもこもこ」は全ページ「シーッ」になっています

そして「わうわう」=犬

最初は「ヴォフヴォフ」というような、本当に犬の鳴き声をその通り真似た音だったのが
「ヲウヲウ」になり、「わうわう」になり。
初めて「ヴォフヴォフ」と言うのを聞いた時は
「何て瑞々しい感性!(?)『わんわん』なんて刷り込まれなければ自分に聞こえた通りに真似るんだ!」
と感激
 し、絶対「わんわん」とは教えない!と心に決めて
し、絶対「わんわん」とは教えない!と心に決めて私も娘のマネをして「ヴォフヴォフ」と鳴いていたのに、
娘の方から1ヵ月ほどで変化してしまいました。
保育園で絵を指して「これはわんわんよ~」なんてやってるんだろうなあ。
またひとつ人間社会に馴染じんだようです。
シュタイナーは幼児語で話しかけないように言っているとどこかで読みかじった気がするけど、
私は反対~。
脳科学的には二度手間だから最初から正式な名称で、とも言うらしいけど、
人間の成長に無駄を省こうという考え方自体が私は怖い。
高校の校長先生が卒業式に言ってたし!
「小さな無駄はただの無駄だが、大きな無駄は無駄ではない。
無駄は文化。これから大いに無駄なことをするように。」
と。
進学校の校長先生が言うことか!と感激しました。(卒業するから言えること?!)
童謡なんかにも「あんよ」などはよく使われているわけだし
美しい言葉の文化として愛しんでいきたい気がします。
私は、小説「赤毛のアン」の続編「夢の家のアン」でアンが言ってたことに全面的に賛成!
(私「赤毛のアン」フリークです
 )
)アンが生まれてきた赤ん坊に「○○でちゅね~」と話しかけるのを見て
「妊娠中に読んでた育児本に通り幼児語は使わない!宣言してたのはどーなったわけ?」
とギルバートがかわかうと
「こんな可愛いらしい赤ん坊を目の前にして使わずにいられないわよ!そうでちゅよねえ?」
という意味合いの返事をするのです。
でも、牛乳のことを「にゅうにゅう」とかは、保育園に行って初めて知りました。
最初何のことかわからなかったもの。
お茶は「お茶茶」とか。ここまでくると業界用語のような感じがしてきます。
人が幼児語で赤ちゃんに話しかけているのを見ると嫌な人もいるらしいので、
私は子どもと2人の世界の時だけでいいかなあ、と思っています。