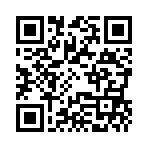2010年03月01日
「センス・オブ・ワンダー」
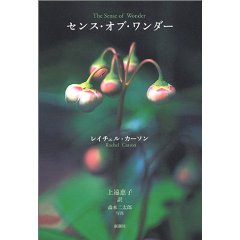
散文詩のような本です。
難しいことはいらない、ただ自然の繰り返しの営みの美しさを感じられる人は、人生に希望が持てる、という言葉(実際はもっと美しく書かれています)に、子どもにもそれを無言のうちに伝えられる自分であったら、と思います。
余談ですが、先日上司との雑談の中で
「お金持ちの人っているもんですねえ。」
とため息まじりに言ったら、
「お金持ちの人生なんてつまらんよ。ギリギリのところでもがくけん、人生は楽しいとたい。」
と即答され、かっこい~!と惚れ直してしまいました。
レイチュルも、最初から選び放題選べる人生だったら、きっとこの本に到達していなかったのでしょう。
有名な人ですが、家族を支えつつ科学者でありながら作家の夢を実現した、彼女の強さにも惹かれます。
2010年02月23日
クーヨン3月号「子どもがのびのび育つ家」
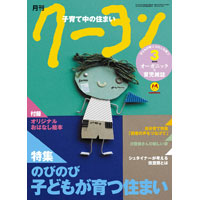
インテリア好き・模様替え好き・ビフォアアフター好きの私なので、
即買いしてしまいました♪
我が家はマンション賃貸住まい。
私も連れ合いも新築マイホームの夢は持っていない人間です。
でも、私はだんだんと土のある家に惹かれるようになってきたので、
賃貸でもいいけど、庭付き戸建に住みたいなあとも最近思います

しかも、古いけれど手入れされているものが好きなので、中古がいいな

まあまだ妄想段階なので、特に現実化しようとはしていません。
さて、今回の特集で一番「
 そっかあ」と気付きがあったのは、
そっかあ」と気付きがあったのは、建築士さんの
「最近、お年寄りのクライアントさんから『ボケない家を』とリクエストされて、
階段だらけの家を作った。」
というお話。
ユニバーサルデザインでバリアフリーな時代に逆行です。
しかし、確かに私も何でも電動な便利な住まいの中で、何となく違和感を持っていたのです。
例えば、お風呂の給湯器が
「♪残りおよそ5分でお風呂に入れます」
「♪お風呂が沸きました」
とお知らせしてくれます。
何度ビクっ!としたことか。
娘は誰かがあの中に住んでると思うようになるんじゃないかと懸念しています

セキュリティをかけたまま窓を開けると、システムに住人が警報を鳴らされたり

(1回でかけるのをやめました。ちょっと使ってみたかった
 )
)玄関のドアは電気錠なので、はっと気付いた時には締め出されちゃったり。笑
こうなると、警備会社が来るまで30分以上待ちぼうけ。
私が子どもの頃は、お湯と水を少しずつ出してちょうどいいお湯の温度にし、
20分くらい経ったら「もう溜まったかな?」と見に行ったり、
忘れていて溢れさせ、もったいない
 っていう思いをしたり。
っていう思いをしたり。算数の問題でも、「1分間に○リットル溜まるとすると・・・」なんで文章問題があったけど、
ボタンひとつで機械が溜めてくれるんじゃあ、実感も湧かないよね・・・
それとも、そんな問題自体、もう廃れてしまっているんだろうか。
うちにはひねる蛇口がひとつもありません。
現代っ子は雑巾を絞れない、なんて聞ききますが、
こういう日常的な動作ひとつひとつが省かれていく中で
身体技術が失われていくのでしょうね

ユニバーサルデザインやバリアフリーを必要としている人はいるし、
誰にでも使いやすいことは確かだけれど、
自分の力で動かすってことを普段の暮らしの中で自然にやっていくことで
モノに頼らない体づくりができそうです。
現状では街なかに住んでいるので、とてもじゃないけれど外で遊んだりできません。
環境も含めて、子どもが大きくなる中で考え直さないといかんかなあ・・・と思う今日この頃です。
2010年02月14日
「えんやらりんごの木」
一体何をやるのかしら?
と思っていたら、みんなかさ地蔵役で(笑)
先生方が「1歳が何ができるだろう?」と一生懸命考えてくださったんだなあと
よく伝わる劇でした。
劇の中にわらべうたを取り入れて、親も一緒に踊って・・・
少人数のクラスだからできる、アットホームな会でした

終わった後、お土産に絵本をいただきました。
運動会のお土産はプラスチックのおもちゃだったのでノーサンキューだなあ
 と残念だったのですが、
と残念だったのですが、(役員会で決めたもので、その場でよっぽど意見を言おうかと思いましたが意外に賛成の意見が多く・・・
まあ今年は初めてだしそのうちね。と思い黙っておくことにしました。)
今回は事前に先生から「この3冊のうちどれがいいですか?」と選ばせていただけて、
心遣いに感動
 選書も素敵でした
選書も素敵でした
「だるまさんがころんだ」も、最近娘がハマっているようなのでちょっと悩みましたが、
絵のタッチに惹かれてこちらを選びました。
↓

保育園でも読んでもらっている絵本ということで馴染みがあるようで、
いただいてから選ぶのはこの本ばかり

今日はたくさんのお友達がうちに遊びに来たのですが、
娘は一人で部屋の隅へこの本を持って座って
♪え~やらいんごのき♪
と歌いながら自分の世界に浸っている姿が見られました。
たまたま、白に赤のイチゴ柄のお洋服を着せていたので、
絵本と色がマッチしていて、いや~ん可愛い
 と
と遠くからこっそり目がハートになっていた私でした

2010年01月27日
「ぐりとぐらのうたうた12つき」

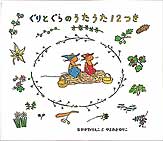
「ぐりとぐらのいちねんかん」と隣同士に置いてあったので、
「どう違うの?」とどちらも読んでみましたが、あまり変わらない。笑
紙の質感は「いちねんかん」の方が好きだったけど、
中味はなんとなく「12つき」の方がいいと思ったので(なんでだったかな?忘れたけど)
こちらにしました。
娘は「ぐりとぐら」が大好きで、いつも
「ぐい ぐあ ぐい ぐあ♪」
と言いながら、体を揺らして聞いています。
読む方としても、リズミカルなので節をつけて読みやすいです。
「12つき」はさらに歌のような文になっているので、
さながら絵本のミュージカルみたいです
長い文章はまだじっと聞いていられなくてページをめくりたくなってしまいますが、
歌だとゆっくりしっかり楽しめるようです。
「ぐりとぐら」の絵は、私が子どもの頃に引き込まれていた絵本「わたしのおうち」と
同じ方によるもので、同じ世界観を娘も気に入ってくれているのが嬉しくもあります。
春の畑の野菜のはっぱがちゃんと種類によって違う形だったり、
9月の台風一過の青い部分が覗く空模様だったり、
ステレオタイプなだけじゃない繊細な四季の移ろいが本当によく表現されているなあと感心してしまいます。
一番気に入ったのは、12月がクリスマスじゃなく「ぼうねんかい」なところ。笑
「いちねんかん」の方もクリスマスじゃなかったので、意図的なのかもしれません。
クリスマスについてどう教えようかまだ考え中なので、ここは結構ポイントでした☆
イエス・キリストは好きですが、私はクリスチャンではないし、
商業ベースの浮かれクリスマスに乗るのも違うかなと。
独身時代の恋人同士なら乗っかっちゃえばいいと思うんですけどね、
子育てにそれを適応してもいいものか?
来年のクリスマスくらいにはだいぶわかるようになってくると思うので、
それまでにゆっくり考えようっと

何だかクリスマスの話になってしまいましたが、そのことはまた別の機会に書こうと思います。
2009年09月07日
「まてまてまて」
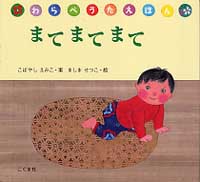
edibleさんのブログで「ととけっこう よがあけた」のレビューを見て、
図書館で借りてきて、それもとってもよかったのですが、
シリーズもので見つけたこちらの「まてまてまて」の方が娘にはツボだったらしく
あまりにお気に入りなので購入しました。
「わらべうたえほん」とありますが、ほぼ「まてまてまて」の繰り返しのみ。
適当~に節をつけて読んでいます。
毎日寝る時間が近くなったら
「ねえ、『まてまてまて』は?」
と声を掛けると、置いてある方にダッシュ

部屋を暗くして手元の灯りだけにし、
「はじまりはじまり~」
と絵本を開くと、パチパチパチ
 と手を叩きながら絵本に正対して座ります。
と手を叩きながら絵本に正対して座ります。目がわくわくしているがわかります

「まてまてまて~」
とハイハイしている赤ちゃんをいろんな動物のお人形が追いかけるだけのシンプルさですが、
それが娘には楽しくて仕方がないらしいです



最後にお母さんが出てきて
「つかまえた」
とつかまえるページで本当に一緒にギュウして娘をつかまえて、次のページで登場人物(?)がみんな
「おやすみなさい」
とネンネしちゃうので、一緒にごろりと横になり、絵本に
「バイバーイ
 」
」と手を振って、キューピーちゃんをカゴのベッドに横たわらせハンカチの布団を掛け
「ネンネ~」
とトントンしたら、もうオネムの時間です

この本を読んであげている間に「ネンネ~」と言えるようになりました。
卒乳していないのでここからオッパイで十数分~二十分くらいで撃沈するわけですが、
保育園に通いだして日中たくさん遊んで疲れるというのもあるのでしょうけれど、
この「まてまてまて」儀式のおかげでどれだけ昔と比べてスムーズに寝てくれるようになったことか

夜中まで格闘していた日々が嘘のようです
 (遠い目)
(遠い目) 2009年08月31日
クーヨン9月号
もうそろそろ10月号が発売されちゃいますが、9月号を買いました。
特集は「子育てに生かすモンテッソーリ教育」↓

モンテッソーリは「教具」を用意してお仕事をやらせる、というところが何となく腑に落ちていないのですが、
「平和のための教育」「敏感期」などのキーワードは気になるのでもっと詳しく知りたいなと思って、
数か月ぶりに購入。
読んでみたら、今までよりも「いいじゃん」「なるほど」と思う部分は増えました。
たとえば、
・早期教育でなく適時教育
・数を教えるにしても、ただ数字として表わす部分だけじゃなく、子供の中の秩序感の生成から見守る
・教具は整然と置いておけば子どもはその通りに片付けるようになる
とか。
でも、6か月過ぎから鏡を置いて自分を認識させる、なんていうのは、
シュタイナーの「7歳までは夢の中」説が素敵
 と思う私にとっては
と思う私にとってはそんなわざわざ目覚めさせなくっても!という感じがします。
「教具」の数々にしても、なあんか自然じゃないというか、
「子どもに手を貸すだけ」にしてはちょっと大人の意図が見え透いている感じがするんだよなあ。
ともあれ。
マリア・モンテッソーリさんはイタリア・20世紀初頭生まれ。
「こどもの家」を始めた当初はムッソリーニから庇護を受けていたんだけど
独裁者になったのを見てそれを拒否。すごい!
迫害を逃れてスペイン・オランダと渡り歩いた後
インドに招かれ7年間で1000人を超える教師を養成。
「子どもの家」を各地につくりました。
その験から、平和が大事!という境地に至って
「世界には戦争ではなく、平和をつくるための教育が必要」
「平和は子どもからはじまる」
「子どもが居場所を得て環境を愛することが平和に繋がる」
という結論に至ったんだそうです。
どの言葉も今を生きる私たちにこそ必要に思えてなりません。
優しくてパワフルなおばあさまだったんだろうな、と想像します。
きっと、傍にいたらシュタイナーより好きに違いない。笑
モンテッソーリの平和教育には共感するし
細かい点では「なるほど
 そのアイディア使える♪」と思うことが多々あるけど
そのアイディア使える♪」と思うことが多々あるけどやっぱり全体としては私の中ではシュタイナーに軍配が上るな

というのが感想でした。
2009年08月15日
「おおきなかぶ」

我が弟が、姪っ子(私の娘)のためにお盆の帰省のお土産として買ってきてくれました。
前回帰って来た時に、何かの話から
「よし、今度『おおきなかぶ』を買ってきてあげよう
 」
」と宣言してくれていたので、この挿絵のイメージが湧いて早速ネットで検索

有名な話だから他にもあるのかもしれないけど、ぜひとも福音館のこのバージョンがいいなあ、
と思っていたら、まさにその通りのものだったので感激!
弟、ナイスチョイス

幼稚園の年中の時、学芸会で孫娘役をやったのでなんだかとっても親しみのある「おおきなかぶ」。
デッサンの精確さを感じさせつつ情緒ある挿絵が素敵☆
疲れて腰掛けてるおじいちゃんとおばあちゃんが何とも言えません

中身の絵とはギャップのあるタイトルの扉絵もナカナカのセンスです

裏を見たら800円でびっくり。
と思ったら、「ぐりとぐら」も800円でした。
絵本って、フルカラーなのに安いのね!(ものによる?)
著者を見ると「トルストイ再話」って。
再話ってどゆ意味?元々ロシア民話なのをトルストイが掘り起こしたのかしら。
トルストイも小学生の頃かなり図書館で借りて読んだので親しみあり。
内容は全く一つの話も覚えてないけど・・・
母に「トルストイ読んだら?」的に促されて借りていた気がするなあ。
娘はというと、弟のところに絵本を持って行って膝に乗せて!と要求し
これを読んで!と指さして何度も読んでもらっていました。
「うんとこしょ どっこいしょ」
の繰り返しが小さい子にも楽しいのでしょうね♪
2009年08月14日
「シュタイナー入門」

新書。
やわらか~くかみくだいたシュタイナー教育についての本しか読んだことがなかったので
広く深い人智学ってのは一体どんなもの?それからシュタイナーさんってどんな人?
というところを広く浅く知りたくて、買ってみました。
が、それは無理なことでした。
むずかしー!!んです!
私の読書の時間は夜布団に横になってからなので、
何度も「??どこまで読んだっけ?」と辿らないと意味がわからない。
ゲーテとかフィヒテのあたりは、だいぶ根気強く何度も読み返してみたけど
やっぱり意味不明・・・悔しい!
世界史大好きだったのになー。山川の教科書引っ張り出したくなりました。
あと数ページで終わるので、とりあえず読み終わってから。
勢いがないと読み終えられそうにない

入門でこれじゃあ、シュタイナーの著書なんて読めるのか?!
難しい難しいと言われるので、いつかは!と思っているけど、道のりは遠い

でも、この著者はなかなか魅力的でした。
この人が大学のゼミの教授だったら、変人だけど授業は面白そう。
さて、難しすぎてまとめきれないので、紹介文を引用↓
「シュタイナー教育」や「人智学」で日本でも広くその名が知られるルドルフ・シュタイナー。
だが、アカデミズムからは「胡散臭いオカルト」との烙印を押される一方、
受容する側にも、その思想への盲目的な追従、偶像化が見られるなど、
ここ日本でのシュタイナー理解はまだ充分とはいえない。
彼が立脚した第一次大戦下ドイツの時代状況、
また、ドイツ精神史における思想系譜、歴史経維に広範な省察を加え、
その生を内側から活写することで、
「みずから考え、みずから生きること」への意志を貫いた「理念の闘士」、
シュタイナーの思想的核心を浮き彫りにする。
第1章 教育思想の源泉―他者への目覚め
第2章 認識の探究者―カント、フィヒテ、ゲーテをめぐって
第3章 それは「オカルト」なのか?―西洋と東洋の霊性史
第4章 神智学運動へ―ブラヴァツキーの闘い
第5章 ドイツ精神文化の霊学―純粋思考と帰依の感情
第6章 戦争と廃墟の中で―「国民」になる以外、生きる道はないのか!
第7章 魂の共同体―ナチスの攻撃と人間の悲しみ
ここまで↑
よくわかったことは、幼児教育は彼の真ん中にあったことではないということ!
それから、かなり理屈っぽい人間であること。
彼の思想を理解するには、彼の時代までのキリスト教のあり方を知る必要がある。
ローマカトリック教会が正統を保つため異端や異教を弾圧してきた結果、
その多様性は隠れざるを得なくなり、オカルティズムとしてひっそり生きてきた。
そのように一部の人間(カトリックでは神父)だけに神(=霊的なもの)との
交信が限られてきた当時までのキリスト教ではなく、
すべての人に開かれたものにしよう、というのが彼のオカルティズム。
この場合の「オカルティズム」は、日本で一般的にイメージされる「オカルト」とは全く意味が違う。
「オカルト」の語源は「隠されたもの」。
ちなみに日本では宗教的多様性が維持されてきたので
ヨーロッパと同じ意味でのオカルティズムは存在しないと著者は言っています。
唯物論否定。
だからといって、スプーンが曲がるみたいな、物質的にわかりやすいことに
その表れを求めるのは精神的退廃である?
直観よりも考えて考えて考え抜いたところに霊的なものとのつながりがある?
これがシュタイナーを知ろうとすれば避けては通れない彼の思想の真正面なんだって。
私の理解が悪くてニュアンス多々間違ってるかもしれませんが
しかし、教育だけに一生懸命な人生だったわけじゃないのに
それぞれの分野で一目置かれる功績を遺していったなんてすごいなあ。
むしろ全般的に考えていた人だからこそ、すべての分野にそれが活かされているのかもしれない。
もっとバイオダイナミック農法のこととか医学のこととかも出てくるかと思ったけど
この本はシュタイナーの思想を語る本だったので、その辺は全然載ってなかったのが残念。
次はその辺にも触れている本を読みたいな
2009年08月12日
「ペレのあたらしいふく」
娘の保育園の貸し出しで自分が読むために借りてきました。

娘は、文章が長すぎて食いつかず。あと1・2年、いや3年後くらいかな?
お説教がましいところはひとつもなく、
ものが自分の手元にやってくるってどういうことなのか、
ちゃんと目に見えるように描いてくれています。
レトロチックなタッチも好み

背景の細かな描き込みが楽しい。
そして労働の尊さ、人とのふれあいの中にこそ存在する生活。
一時期はまって読んでいた「大草原の小さな家」シリーズや
大好きな「赤毛のアン」シリーズに通じるものを感じます。
是非とも欲しい1冊になりました!
後から、著者ベスコフは、私の大好きな松井るり子さんの大好きな絵本作家だったことを知って、納得!!
2009年08月10日
「よあけ」
貸出は2冊まで。
以前から読みたいと思っていた「よあけ」を見つけたので、自分用に一冊借りちゃいました☆
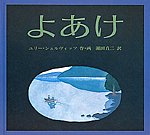
静謐な朝の空気をそのまま切り取ったような絵本。
添えられた言葉も絵も詩の一部のよう。
主人公はどちらでもなく、自分のイメージの中にある夜明け。
自分でも忘れているいつかの夜明けへの、旅の入口となってくれます。
ちょっと中国っぽさを感じていたら、やっぱり宋時代の中国詩をモチーフとしたものでした!
色の放出が眩しい最後のページは、
色づかいがシュタイナー教育で用いられるにじみ絵に似ているなあと思いました。
淡々としたページが続いているところに突然ぱあっと光が射して、一瞬ドキン!
心をぐっと掴まれました。
借りるだけでなく、欲しくなっちゃった(>_<)
2009年08月08日
「もこもこもこ」

もっと娘が小さいころ見せても無反応だったのに、
1才過ぎた今はこの絵本が一番のお気に入り。
何度か読んであげていたら、最近は部屋に落ちているのを見ると拾ってきて
自分で
「バフンッ!ボム!ダーッ!」
とか何とか効果音付きで音読しています。笑
こういうシンプルなものに反応がいいと、親の勝手乍ら嬉しくなっちゃいます。
私はこの本を初めて見た時は、微妙に不協和音的な色合わせに胸がざわついて
何だか好きになれない気がしていたのです。
それが、娘にせがまれ何度も何度も味わううち、美しいグラデーションのページよりも
そっちの違和感の方が気になってじーっと見入ってしまうようになりました。
色彩もさることながら、言葉と造形どれをとってもぴたりと当てはまる。
詩人の仕事だあ~。
さすが谷川俊太郎。
この本を見て、谷川俊太郎の守備範囲の広さに夫と驚きました。
鉄腕アトムの歌の作詞も彼なんですってー。
きっと物凄いバイタリティの持ち主なのだろうと想像します。
写真も、ピカソにそっくりの目をしているし。
谷川俊太郎をテーマにしばらく追いかけてみる気になっています。