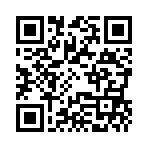2009年09月30日
お母さん記念日
「お母さん」
と言おうとしました。
「きゃーしゃ」
と
「たーしゃ」
の間くらいの音。
私を指さしながら言ってくれたので、意味もわかっているようです。
妊娠中、連れ合いと「何て呼んでもらおう?」と考えた時、
私は断然ハウス名作劇場ばりの「かあさん」「とうさん」がいいと主張したんだけど
彼は「普通でいいんじゃない~」と言うので、
「お母さん」「お父さん」に決定。
だから「お母さんよ」「お父さんだよ」としか教えていないはずなのに、
周りがみんな「ママ」「パパ」だし、
保育園でも先生方が「○ちゃん、ママ/パパがお迎えに来たよー」とおっしゃるので、
すっかり覚えてしまい、言い易さもあって、
「ママ」「パパ」とは少し前から言えるようになっていたんです。
でも、自分たちで決めた呼ばれ方なので、しつこく
「ねえねえ『おかーさん』って言ってよう」
とお願いしていたのですが、なぜか恥ずかしがって絶対に言ってくれない日々が続き。
昨日もダメモトで「『おかーさん』は?」と話しかけたら
気が向いたらしく、言ってくれたのです。
夕方、お友達に電話でその話をしたら、
「ねえ、1才過ぎてから、前よりもっと子どもが可愛くなったと思わん?」
と言われ、まったく私も思っていたところで
「思う思う!」
と盛り上がりました。
単に一緒にいる時間が長くなるほど愛着が増すということもあるでしょうし、
しゃべり始めたりして反応してくれるというのもあるのでしょう。
昔、中学の頃受験勉強の合間に一心に読んでいた「大地の子エイラ」という小説があります。
エイラはクロマニヨン人なのですが、捨てられてアウストロラピテクスに拾われまます。
アウストロラピテクス達は言葉を持たず、感情表現も乏しい中、
エイラ一人が笑ったり涙を流したりする様子が自分たちと違うことで、いじめます。
大きくなったエイラは村を追い出され旅をしていると、自分と同じクロマニヨン人と出会い、
初めて自分と同じように笑ったり泣いたり、声の出し方で気持ちを伝えたりすることを知り、
やがて恋をする・・・
というお話。
上・中・下3冊×5部くらいまであるという巨編で、
前半は辛くて先が果てしなく感じられ、読むのをやめようかと思うほどでしたが、
気持ちが通い合うシーンから物語がぐっと面白くなり引き込まれました。
それまでの私は環境問題にとても心を痛めていて、
「大きくなったら環境問題に関する仕事をする!」と宣言していた
(正確に言うと「環境庁に入る!」と
 環境と名のつくものはそれしか思い浮かばなかった)
環境と名のつくものはそれしか思い浮かばなかった)のですが、この本を読んで夢が変わりました。
「コミュニケーションてこんなに人の心を惹きつけるものなんだ。
私たちが言っている『環境』も結局は人間にとっての環境なんだ。
感じたり考えたりできる一人一人の人間って何てすごいんだろう。
やっぱり、そういう『人間』を大事にする職業に就きたい。
一人でも、人為的に辛い思いをする人間が少ない世の中にしたい」
と考え、今度は「ユニセフに入り、貧困問題に携わりたい」と思うように。
(相変わらず大きいところしか目に入ってませんでした
 )
)それくらい、私の人生を大きく変えた本なのですが、
昨日の「おかあさん」もまた、私をエイラのところまで引き戻しました。
コミュニケーションがどれほど人間にとって必要なものなのか。
人生の折々に、この本をまた思い出す気がしました。
新生児の頃は特に、自分から出てきたというのが信じられないというか
親という実感がないまま、ただただ新生児のの可愛らしさに引っ張られるように
お世話をしてきたような気がします。
昨日やっと、お母さんになれたような気がして、
通園中の墓地を娘を抱っこして、泣きながら歩いた朝でした。
2009年09月27日
ハーブラボのシャンプー
家族はそうでも自分だけは合成界面活性剤でないシャンプーを使ってきた私です。
中には、背に腹は代えられず、という時代もありましたが、
基本的にはあらゆる石けんシャンプーやアミノ酸系を試してきました。
そして辿り着いた、私の中の究極のシャンプーがこれでございます


ハーブラボナチュラルケアヘアシリーズ。
他にシトラス(ノーマルヘアタイプ)とローズ(センシティブスキンタイプ)があるんだけど、
私は全部試した上で香りで選んでラベンダー(ダメージヘアタイプ)が好き

何故このシャンプーが究極かと言いますと。
私の中のシャンプー選びポイントをすべてクリアしているのです。
・石油系合成界面活性剤を使っていない
→洗浄成分がアミノ酸系。
・弱酸性
→娘にも使いたいので、目にしみないように。
また、石けん系だとアルカリ性なので、弱酸性に戻すためにリンスも買わなきゃ(クエン酸水でもいいけど)いけなくなる。
・動物実験をしていない

→世の中のほとんどの化粧品は・・・してるらしいです。
・天然由来の香り
→合成の香りが嫌い

ハーブラボの香料は、「ヴェレダ」のエッセンシャルオイルを使用しているのです!何という贅沢

と、言いますのも。
ヴェレダWEREDAはシュタイナーの提唱している人智学に基づいて作られた自然化粧品のブランド。
可能な限り、バイオダイナミック有機栽培農法か野生の植物を使っているのです。
ヴェレダのロゴ。
↓

シュタイナーが命名したらしいです。
西暦紀元初頭に実在した、治療をする女祭司(尼僧)の名前だとか。
バイオダイナミック農法とは?
ヴェレダのHPより引用。
↓
「通常の有機栽培とは違い、さらに一歩進めて、自然の持つパワーまで取り入れたのが、バイオダイナミック有機栽培農法です。化学肥料や殺虫剤を使わない点では有機栽培も同じですが、異なるのは宇宙の力まで取り入れ、地球と植物のリズムを考えて栽培すること。シュタイナーが提唱した、まったく独自の農法です。
バイオダイナミック有機栽培農法は、大地を育むことからはじめます。それは栄養を与えることではなく、大地そのものの生命力を高めるという考え方です。
たとえば、粉末状にした水晶などの鉱物、カミツレ、ノコギリソウなどの植物、牛角糞などの動物由来のものを調合した、数種の堆肥を与えます。地球に存在する無機物と有機物を合体したものを与えることで、大地の感受性を豊かにするのです。天体や地球からの力を受けやすくなり、それによって植物のパワーもさらに高まります。」
前にも書きましたが、私が20代前半にフェアトレードの会社にいた時に取り扱っていた紅茶がバイオダイナミック農法で、インドの生産者ツアーで農園を訪れ、バイオダイナミック農法を目の当たりにし、それはそれは驚きました。
ただの有機農法じゃなく、たとえば新月の夜に種を撒いて、満月の夜に収穫するとか、植物によって呼応する鉱物をその植物を植える予定の土の中に一定期間埋めておくんだったかな?
いや、牛の角の中に土を入れて冬中埋めておくんだったかな?
あと、たしかその土を水がめに入れて延々と棒でかき混ぜる!
同じ方向ばかりじゃなくて、10回回したら今度は逆、とか。
かき混ぜてると、渦が出来て円錐状にえぐれてきて、
そのとっぺん先に宇宙のエネルギーが凝縮され、
逆回転させることでカオスを起こし、
またかき混ぜることでさらにエネルギーが高まっていく、みたいな!(すいませんニュアンスで
 )
)もう6年位前のことなのでかなりおぼろげですが、
魔女みたいなことを真剣にやってる人たちがこの現代にいたなんて!と衝撃的でした。
しかもそこはインドの山奥、ネパールが見えそうな田舎ですよ。
その村のことはまた改めて書くことにします。長くなるので!
とにかく、バイオダイナミック農法というのは、単なる有機農法よりもさらに気の遠くなるような
手間隙とエネルギーがかかるものなんです。
ありがたい~

何の話がわからなくなってきましたが、ともかく、そんな私的基準をクリアしたハーブラボのシャンプーを昨日買いました。
最近はパックスオリーの泡タイプだったのですが、連れ合いは石けんシャンプーのきしみが嫌いで
(オリーはあんまりきしまないと思うんだけど・・・)
「メ○ットがいい」と言うので我が家のお風呂には何本ものボトルが並ぶはめに・・・
次に使うならハーブラボというのが頭にあって、でもモノとしては素晴らしいけど1680円税込って、
やっすい合成シャンプーなら100円台で買えるのにやっぱ贅沢かなあ・・・とかうじうじしているうちに、
オリーが切れてうちにはメ○ットしかないという状態に!
1歳の娘にも、あの阿蘇火口のような色を使うたびに「いや~ん
 」と毎日思うくらいなら!
」と毎日思うくらいなら!とやっと覚悟が決まって、ちょうど昨日魚屋町のピュアリイに入っているエコショップSEOさんに行った際、
久しぶりに購入したというわけです。
長い。
これならきしまないから連れ合いも使うかもしれないぞ。
そしたら、結局安い合成シャンプーとどっちも買うより、安く上がるかも

久しぶりに使ってみると、香りにうっとり~

今朝起きてからも手触りが全然違う~

あー早く戻ってくれば良かった。
もう浮気はしないと思います。多分。
2009年09月26日
くまもと森づくり活動の日
「森林の公益的機能を発揮していくためには県民が森づくりに参加し社会全体で森林を守り育てていくことが必要」
との趣旨で去年から始まったそうです。なるほどなるほど。
それもだけど、娘がドングリ拾い
 しているところを想像したら萌~
しているところを想像したら萌~ っとなっちゃったので
っとなっちゃったので連れ合いに「ねーねーいこうよいこうよいこうよー」と誘って家族で参加することにしました。
定員がありますので、お申し込みはお早めに!
**************************
 くまもと森づくり活動の日イベント
くまもと森づくり活動の日イベント
日程 : 2009年11月8日(日)
時間 : 午前8時15分~45分 集合受付
午前9時~(30分程度) 出発式@県庁プロムナード
→ 貸し切りバスにて現地移動
午前10時~午後3時(予定)
熊本市近郊の3箇所に分かれて活動
会場 : 1.熊本市立田山憩いの森 「森を知る、体感する」:自然観察を兼ねたドングリ拾い、丸太切り、ネイチャーゲーム
250名程度(子どもや家族連れの参加のみ)
2.熊本市小山山 「森と人の関わりを知る」:竹の伐採による里山整備 125名程度
3.菊池郡大津町「森の恵みを知る、森を育てる」:ヒノキ20年生の枝打ち・間伐 125名程度
参加費 : 無料!簡単な昼食と保険つき☆
*作業ができる服装で参加ください。
*集合及び解散場所は熊本県庁。自家用車は北側駐車場に駐車。
申し込みは、参加者氏名、フリガナ、性別、郵便番号、住所、携帯電話番号、年齢、生年月日、参加希望コース(第2希望まで)
を書いて、郵送またはFAXまたはメールなどでお申し込みください。
締め切りは10月20日(火)。
申し込み先 : 熊本県農林水産部森林整備課みどり推進班 山田さん
TEL 096-333-2441
FAX 096-383-7704
e-mail yamada-t-dq@pref.kumamoto.lg.jp
2009年09月21日
森のようちえん体験会に行ってきました♪
ブログに「行けない」と書いていたのですが、急遽仕事がキャンセルになって!
あまりに嬉しくて、糠喜びしたくなくて、
「ほんとにいいの?やっぱり来いとかもう、いやよ?大丈夫??」
としつこく確認しちゃいました。
八代に午前9時半着のつもりが、子連れの道中はやっぱり何かと時間がかかり、
当てずっぽうではやっぱり辿り着かなくて、遅刻(><)
待っていてくださって、出発には何とか間に合いました

私たちが着く前には以前の様子のスライドを見ていたようです。
出発前に子どもたちの点呼があり、ようちえんらしくなってきた~



参加していたのは多分10家族くらい。
3ヶ月のRくんはママの胸に抱っこ紐で安心しています。
一番大きかったのはもうすぐ5歳のYちゃんかな?
それぞれが、それぞれのペースで歩きます。
最初が難関、吊り橋↓

真ん中あたりに「飛び込み禁止」って書いてあったけど、飛び込む気には普通はならないはず。笑
みんな固まってしまって、ママパパに抱っこされて渡った子がほとんどでした

道路を歩いている間も、ガイドの方たちが
「もうすぐ車が来まーす」とか、しっかり見ていてくださっているので、安心。
もちろん我が子のこと見てるつもりなんだけど、何せ大所帯だから紛れるんですよね~

土手の階段を下りて河原に到着したら、みんなで岩に座って
お世話してくださった幸山さんが「センスオブワンダー」の一節の朗読してくれるのを聞きました。

街の中にいたって、アパートに住んでいたって、
子どもと自然を味わいたくば、ただ、空を見上げればいい。風の音を聞けばいい。
そういうような内容でした。
まさに、私が娘に自然の中での育児じゃなくて申し訳ないなあと思っている、
その部分を許してくれる文章でほっとしました。
静かな時間を過ごした後は、お待ちかね、川に入ってのピチャピチャタイム

娘は我先にざばざば入って行き、当然一番にズブ濡れになり、
一番にツコケテ顔からバッシャーン
 いえ、水着ではありません。
いえ、水着ではありません。まあ、想定内ですが、全着替えです


短い時間でリズムよく切り上げて、もと来た道を帰ります。
水に入ってすっかり調子の出てきた子どもたちは
思い思いに葉っぱを拾ったり、椎の実を見つけたりしながら元気に歩きます

娘は私の手を振りほどき、一人でやるんだと主張して、
ヨチヨチ+ハイハイで土手の階段を登って行きました。
一度、顔面から地面に激突していましたが、泣かずに前進

帰りの吊り橋はみんな楽しく歩いて渡れていて、一日で子どもたちの成長が見て取れました

管理棟に戻っておやつまでいただけて

私自身も小中学校の同級生とばったり会ったり☆
にじみ絵教室の方と示し合わせていないのにまたお会いできたり♪
幸山さんの服にそっとかまきりさんがくっついたままでいたのも印象的でした。
居心地よかったんだろうなあ~。
持って行ったお弁当を食べて、あーいい気持ち。
娘もたっぷり遊んだおかげで、帰りの車中はぐっすり!
行けてほんとによかった~

そして、行けなかった方に朗報です

9月の無料体験会はこれでおしまいですが、実はこれからなんと1回500円で毎週やるらしいです!!
↓
****************************
森のようちえんサタデー
9月26日・・・初秋の里をお散歩
10月3日、24日、31日・・・どんぐり拾いなどお散歩
いずれも10:00~12:00(9:30~受付)
参加費お子様一人500円(親子の保険代を含んでいます)10組程度
10月17日は里地での棚田の稲刈り体験親子1800円・昼食付
 、一人追加600円。
、一人追加600円。安いでしょ~!
10月22日(木)は「森のようちえんえんがわカフェ~氷川町のびのび子育て親育ち事業~」(毎月開催予定)
第1回として里地屋敷で味噌作りだそうです。
9:30~15:00(9:00~受付)、参加費は手作り味噌2キロ材料費・昼食込み親子3500円、5組限定。
盛りだくさんですね~。
詳しくは、立神峡公園のHP
http://www.tategamikyou.com/
をチェックしてみてください♪
2009年09月21日
田舎の一日

南阿蘇村にあるばあばあちゃんの家まで、市電とJR、南阿蘇鉄道を乗り継いでの約2時間。
途中、外国人ツーリストと仲良くなったり(4人も。今日は観光客が多かったな~)、
車窓からの風をびゅうびゅう感じたり

私の妹も一緒で、抱っこしてくれたりしてたいそう助かりました♪
さて、ばあばあちゃんちでは最初は少し固まっていた娘ですが、
お盆に行ったばかりだったこともあってじき慣れたよう。
ばあばあちゃんにせんべいを食べさせたり
 ごはんを食べさせてもらったり、
ごはんを食べさせてもらったり、なかなか打ち解けておりました。
二人を見ていると、小さい子どもと老人ってなんだかペースがかみ合ってるな~って感じました。
二人とも、急ぐことはない・必要もない生活だもんね。
ほんとはみんなそうなんだろうけど、きっと急がなきゃいけない気がしているだけ。
たしか、シュタイナーの何かの放物線でも幼年期と老齢期が呼応しあっていたような?うろ覚え・・・
午睡の後は、ビニルハウスの水遣りに付いて裏の畑へ

巨峰の棚、芽を出したばかりの小松菜の畝、オクラ、
種から蒔いたクリスマスローズの鉢、物凄く太い夕顔、
その他お花さんたちに水を遣るのにたっぷり数十分はかかります。
その間娘は桶の中をひしゃくでかき回すのに熱中し、もちろんビショビショ。
その足で畑を歩いて靴は土みどろ。
いいぞいいぞ♪だんだん田舎の子になってきた

畑の際にはざくろの木が植わっていて実がたわわ。
採っていいよと言われたので娘にプレゼント。

水遣り後戻ってきたら、里芋の葉の上に並べてありました。

柿も空に鮮やかに成って、秋の色です。

2009年09月17日
自然の歌
ツクツクボーシ♪が聞こえてきました。
私、蝉が世界で一番嫌いな虫なので(本当に、見ると寒気がします
 )
)ツクツクボーシの本名が何なのかもわからない体たらくですが(いや、本当の名前なんでしょうか??)
見るのは嫌いでも、蝉の声に風情を感じたりは人並みにしますよ

で、ツクツクボーシ♪が鳴きだして、声のする方の木をじっと見た娘は、
次の瞬間ツクツクボーシ♪のリズムに合わせて踊りだしました



音楽が大好きで、隣のクラスの歌にも反応して踊っているという娘。
彼女にとっては、ツクツクボーシ♪は歌だったのです!
娘がまだお座りができなかったくらいの頃に、
私の父の家の盆栽のもみじの葉っぱが窓辺で風に揺れているのに向かって
手を振っているのを見た時と同じ感動がありました。
彼女にはもみじが手を振っているように見えたのでしょう。
自分の手がもみじみたいなのに、もみじに向かって手振ってる!って、一句捻り出したくなりましたよ。
あ、でも何て詠んだかもう忘れちゃったなあ・・・
子どもと自然とのつながり方って、こういう風なんですね。
2009年09月14日
にじみ絵作品展の様子
ご紹介させていただきます



にじみ絵の作品そのものを額縁にしたり
折り紙の要領でランタンをつくったりの工作も楽しかったそうです♪


きれ~い

展示しきれない作品もあって、作品を入れ替えようかと思っているそうです。
ひとつひとつに驚きがあるので、どんな作品が出てくるのか楽しみですね!
2009年09月14日
これかあ!

色別に並べてあるなんて、初めてのことです。
今までは私が並べるのを壊して楽しんでいる方だったのに。
モンテッソーリの数に関する秩序の敏感期、第一波来た?!
これで、つれあいの仕業だったら笑える・・・
と思って一応確認したけど違いました。笑
2009年09月10日
「生きる力を育む」シュタイナー教育 秋の講座
**********************************
 「生きる力を育む」シュタイナー教育 秋の講座
「生きる力を育む」シュタイナー教育 秋の講座
3回コースで、下記の日程で行われます。
時間・場所・用意する物は各回同じです。
<日程>
①9月24日(木)
②10月22日(木)
③11月13日(金)
<時間>
10:30~12:30
<場所>
大津町オークス・プラザ2F ふれあいホール
<参加費>
1700円 (託児 一人300円 二人500円)
<用意する物>
エポック・ノート(orお絵描き帳)。クレヨン。
<講師>
鈴木裕子さん
<内容>
*前半1時間:芸術体験
シュタイナー教育の方法で「色」や「形」を体験していきます。
まるで初めて出会うかのように、世界と新鮮に向き合ってみましょう。
全回参加が原則。1,2回でもOK。
*後半1時間:学習会と話し合い
シュタイナー教育の本質と現代的姿を学んでいきます。
↓参考図書「シュタイナー教育」クリストファー・クラウダー著 遠藤孝夫訳 (イザラ書房)

課題箇所をコピーして実費でお分けしますが、できれば本を購入して読んできて下さいね。
<主催>
熊本シュタイナー教育芸術の会
<問合せ先>
このブログの「オーナーへメッセージを送る」からいただくと、
私みみもとから主催者へ転送いたします。
パソコンアドレスをお知らせいただくと、より詳しいチラシをお送りくださるそうです。
**************************************
あああ~今回も平日で参加できないな。
と思っていたら!最後にこんな募集が↓
「講座の運営を手伝ってくださるボランティア募集中です。
特に週末の講座希望者で、その運営を手伝ってくださる方大歓迎。」
ナニー!手伝いますとも♪
2009年09月09日
小さな自然
だからこそ、娘が通う保育園は多少なりとも自然の中にあるところがいいなあと思っていました。
保育園選びにあたってはいろいろ調べましたが結局ほとんど選択肢がなく、
とりあえず入れただけラッキー!
その上、すでに何度か書いているように、
気持ちのよい墓地に隣接した保育園に入ることができました。
遠く山も見晴らせます。
車の交通の激しい道路からも一本路地入っているので、
聞こえるのは蝉と子どもたちの声、それから隣の学校の部活の音くらい。
職場からはバスでお迎えに行っていましたが、
あまりにも遅れてくる(とっても遠くから来るので仕方ないのです)ことに耐えられなくなって、
ある日歩けるところまで歩こう、と思って歩き出したら、意外にすぐ着いてしまいました。
所要時間30分。
結局、20分待って10分乗ってたら同じくらいバスでもかかるのです

娘が歩けるようになる前はベビーカーに乗せて家から保育園までの間を歩くことが多かったのですが、
歩けるようになると逆に危なくて、ウォーキングの時間が減っていたところなのでちょうどいい♪
「公共交通機関を使ってる」と書いたばかりですが、
外で過ごしやすい季節になったこともあり、私一人のお迎えに関しては歩くことが増えています。
昨日は道すがら、濃いピンクの今にも咲きそうな花を見つけました。
今朝は、墓地の門の上に出ている白い月を娘が「あ」と指さしました。
本当は、子どもは大自然の中で四季の移り変わりを感じながら育つのがいいんだろうなあ
と思うけれど、諸事情ありそうもいきません。
まあ、優先順位の問題なんですが。
街の生活もなかなか気に入っているのです。
大自然の中に住んでいても家の中で電子機器に囲まれて暮らす人もいるんだろうし。
街なかに住んでいても、熊本では小さな自然がそこかしこにあります。
今まで気に留めていなかった木や花や草を見つけると、
存在するかどうかというよりも、自分が気づくかどうかなんだなあ、と思います。
郊外に行くと「空が広いなあ!」とびっくりします。
そんな驚きも、新鮮でよいかも。
幸い熊本は、ちょっと足を伸ばせばすぐに海・山・川なんでもあります。
なるべく休日にはそういう場所に連れて出掛けて行って、
自分たちの生活の中でできる範囲で自然に触れさせてあげるようにしたいなあと思います

2009年09月08日
冬ごもり
代表を務めている「いいお産の日in熊本2009」の当日まであと2ヶ月を切りました。
(詳しくはうみ つき http://osan.oten-yan.netをご覧ください)
つき http://osan.oten-yan.netをご覧ください)
このイベントをやることになった時、
20代一生懸命お仕事がんばったから、今度は自分のやりたいことをやる30代がやってきたんだ!
20代で培わせてもらったスキルはこういうことためだったのねー♪
と、嬉しくなっちゃいました。
やっと、私の時代(自分の人生の中でね)が来た!(?)
1月に企画してから4月までの間は「育休の間にできることを!」と
スケジュール帳をぎっしり埋めて動き回り、
職場に復帰した5月からは仲間の手を借りながら
仕事と家事の合間の貴重な自分の時間として、楽しんで目まぐるしくやってきました。
しかし、最近、エンジン切れ気味です
9ヶ月間、全然立ち止まってないもんな~。
期間限定だから立ち止まる暇もなかったし。
実際には文字通り走り回っていて、体も秋冬大好きで絶好調なのですが、
後援やら取材依頼やらの書類上の手続きばかりで頭の方がうんざりしてきちゃいました。
みんなに会えると元気出るから、次のミーティングまでの辛抱だ!と言い聞かせつつ、
今はイベントが終わったらしばらくボーっとしたい心境です。
なので、この冬は、家で静かに針仕事の日々にしようと思います♪
作りたいものリストは長々とあるのです
冬ごもりを終えたら、また春から何か始めちゃおうと思います
2009年09月07日
「まてまてまて」
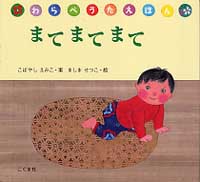
edibleさんのブログで「ととけっこう よがあけた」のレビューを見て、
図書館で借りてきて、それもとってもよかったのですが、
シリーズもので見つけたこちらの「まてまてまて」の方が娘にはツボだったらしく
あまりにお気に入りなので購入しました。
「わらべうたえほん」とありますが、ほぼ「まてまてまて」の繰り返しのみ。
適当~に節をつけて読んでいます。
毎日寝る時間が近くなったら
「ねえ、『まてまてまて』は?」
と声を掛けると、置いてある方にダッシュ

部屋を暗くして手元の灯りだけにし、
「はじまりはじまり~」
と絵本を開くと、パチパチパチ
 と手を叩きながら絵本に正対して座ります。
と手を叩きながら絵本に正対して座ります。目がわくわくしているがわかります

「まてまてまて~」
とハイハイしている赤ちゃんをいろんな動物のお人形が追いかけるだけのシンプルさですが、
それが娘には楽しくて仕方がないらしいです



最後にお母さんが出てきて
「つかまえた」
とつかまえるページで本当に一緒にギュウして娘をつかまえて、次のページで登場人物(?)がみんな
「おやすみなさい」
とネンネしちゃうので、一緒にごろりと横になり、絵本に
「バイバーイ
 」
」と手を振って、キューピーちゃんをカゴのベッドに横たわらせハンカチの布団を掛け
「ネンネ~」
とトントンしたら、もうオネムの時間です

この本を読んであげている間に「ネンネ~」と言えるようになりました。
卒乳していないのでここからオッパイで十数分~二十分くらいで撃沈するわけですが、
保育園に通いだして日中たくさん遊んで疲れるというのもあるのでしょうけれど、
この「まてまてまて」儀式のおかげでどれだけ昔と比べてスムーズに寝てくれるようになったことか

夜中まで格闘していた日々が嘘のようです
 (遠い目)
(遠い目) 2009年09月07日
おうちの仕事
おこづかい
 の話に絡んでの「お手伝い」について考える機会がありました。
の話に絡んでの「お手伝い」について考える機会がありました。お手伝いでおこづかいをあげるのか否か?という話題。
考え方の問題だけれど、と前置きして、講演者ご自身は
家のことのお手伝いは報酬制にしていません、とのことでした。
お金がもらえるからするのか?そうじゃないだろう、と思う、と。
その方はフリーなので自宅で講演の準備などの仕事が発生することもあり、
そういう場合には、例えば「ホチキス100部留めてくれたら100円」というような形の
報酬を渡すことはあります、とのこと。
とても腑に落ちる話だったので、私もそうしよう~っと思いました。
その時はまだまだねんねだったので、いつかのために、という感じでしたが、
先日、NHKの番組「となりの子育て」でお手伝いについてやっていて、
今度はもう娘も立って歩いていろいろなことができるようになってきているので
具体的に「お手伝い」について考えてみました。
まず、「お手伝い」というと、「本来誰かの仕事なのを手伝っている」という感じがするので
「お手伝い」という言葉をやめようと思います。
モンテッソーリのように遊びを「お仕事」として扱うのは抵抗がありますが
家事は「家」の仕「事」なのですから、これこそが「お仕事」という気がします。
ですから「○○(娘)のお仕事」としてそのお仕事の係に任命することにしました。
それから、お仕事をやった時にほめる言葉として「えらい」と言わないようにしようと思います。
家族が家の中の仕事をするのは当たり前だと思ってほしいので。
その代わり、やり方を工夫してうまくなったことや、自分で仕事を見つけてやった時には
めっちゃほめようと思います

なんて考えている間に、娘は勝手に、食事が終わったら食器を重ねて台所まで持ってくるようになりました

途中でもらおうとしても、絶対台所までは渡してくれません。笑
初めてのお仕事です♪
第二弾として、「カーテン開け閉め係」に任命しようと、
朝起きたら「カーテン開けて~」、夕方には「カーテン閉めて~」と頼んで一緒にやってもらっていますが
閉めることしかまだできないみたいです

か、かわゆい。あっすみません
 親ばかだ。
親ばかだ。2009年09月04日
交通公共機関を使うわけ
代々、義父からのお下がり

今時の子育て世代向けな車と違って車高や天井の低いセダンなので
ベビーシートに乗せる時頭を打ちつけてしまう
 のが玉にキズだけれども
のが玉にキズだけれどもあるだけでありがたく使わせていただいています

しかしその車は夫が日中仕事に使うことが多いので、私はバスで通勤。
娘を保育園で降ろしてまた同じ路線のバスに乗り込む、
帰りはその逆を毎日繰り返しています。
会社から保育園まで車なら10分の距離が、バスだと待ち時間が20分+乗っている時間が10分。
保育園から家までは車なら10分、バスだと待ち時間10分+乗っている時間10分+歩き10分。
合計すると、40分も長くかかっちゃう!
しかもその間、夕方で疲れもあり数時間ぶりに会ったもんでおっぱい連呼、
ウナギのように反り返ってゴネる
 娘をなだめすかしつつ、
娘をなだめすかしつつ、自分の荷物+保育園の荷物+抱っこ(もしくはスローモーな歩みにお付き合い)して前に進むのは、
大した距離じゃないのに果てしなく家が遠く感じられ、途方にくれます。
毎日、
「ちょっと無理したらもう一台車持てるんじゃないの?
こんなに疲れるくらいなら車でその便利買った方がいいんじゃないの?」
と考えます。
そして毎日、やっぱりバス通勤を選んでいます。
理由はいろいろあるけど、一番大きいのは色んな人との交流があること。
バス停までの墓地の入口には小学生の女の子が二人、毎日座っておしゃべりしています。
私も帰宅部だった中学生の時毎日友達と公園の入口に陣取っていたのを懐かしく思い出します。
昨日は娘がその前でぴたりと動きを止め見入っている様子。
どうやら食べているアイスクリームに釘付けになってしまったようです

二人の世界なのかな?と思ったけれど、挨拶したら気持ちよく返してくれました。
バス停でもバスの中でも、周りに座った方たちが小さい子どもがいるとなると
目を留めてにこにこしながら見守ってくださいます。
娘は飽きてどんなにご機嫌ナナメになっても
知らない人と目が合うと笑ったり手を振ったりして遊び始めるので
私としては大助かり

今は歩くようになって使わなくなりましたが
ベビーカーを担いでバスに乗り込んでいた頃は
ほぼ毎回どなたかが見かねて手を差し伸べてくださっていました。
本当に、毎日一日で何人の知らない人とお話していることでしょう。
娘もバスに慣れたもので、乗る時には整理券を自分で取り、
降りる時には自分で運転手さんに「はい!」と言いながら渡さないと気がすみません

大抵オタオタして時間がかかりますが、「ゆっくりどうぞ」なんて声を掛けていただくことが多いです。
おかげで、運転手さんには必ず「お世話になりました」とか「ありがとうございました」と言う癖が付きました。
でも、考えてみたらあの巨体を事故せずに目的地まで運転してくれるだけでありがたいことですよね

公共交通機関を使っていて、まだまだスロープ付きや低床バスが少ないとか、
時刻に遅れてくるとか、本数が少ないとか、A地点からB地点へ直接行く路線がないとか、
電停から歩道までの間に歩道橋しかないとか(ベビーカーでどうやって渡れと?!)
いっぱい言いたいことはあるんですが、
それもこれも、使ってみて、バス会社に伝えたりしていかないと変わっていかないんじゃないかと思うのです。
ベビーカーで乗り込もうととっても困っている母子の姿をたくさん見せれば伝わるものもあるのかなと思うし。
助けようかどうしようか、としている方が目の端で見えたら、勇気と声を出して
「すみません、手伝っていただけますか?」
と言うことにしています。
私だったら、言ってもらえた方が手が出しやすいから。
手助けしようかどうか迷って、タイミング合わなくてせずじまいだった時ってすっごくモヤ~ってするし!
たくさん周りに迷惑をかけてお世話になって
「ありがとうございます、おかげさまで助かりました」
と言っている母の姿を、覚えている訳はないけどたくさん娘に見せて
社会ってお互いに助け合うものなんだな、ということを体で沁み込ませたい。
とはいえ、「あーもー誰か迎えに来てくれないかな?!」と思う日がほとんどです。笑
夕方お近くをお通りの際はぜひご一報ください